千葉市中央区みねピアノ教室の峰聖美ですฅ^•ﻌ•^ฅ
少し前に
生徒のYちゃん(小5)と
・スケール・カデンツ・アルペジオを練習しつつ
・24調(各調の持つ響き)のキャラクターを知っていく
ためのレッスンをしていたら
Yちゃんに
「先生は何調が好きですか?」と聞かれて
「えっ…選べない!難しい!
うーん…
c mollやd mollのズドーンと堕ちる感じからの
Es durやF durの清らかな明るさかなぁ💖
あ!けど
cis mollとかE dur
f mollやAs durも
オシャレな響きで大好きだなぁ💖」
という感じで
調(音色のキャラクター)について
生徒さんと盛り上がりました🥰
.jpeg)
このレッスンでやっている
ハ長調やハ短調など、全24調を
頭・お耳・指で理解すると
曲のキャラクター・ピース(曲の性格)を
感じ取れるようになるので
その曲に合った表現や解釈を
自分でイメージ出来るようになってきます🎹✧
以前、別のブログで
ピアノにはざっくり
算数と国語の要素があると思っております。
例えば
一口に読譜と言っても
・音符の名前や意味が理解出来ている
・各リズムをどんな風に弾くのか分かっている
・楽譜のゼクエンツ(同じ所)探しが出来る
・楽譜をパッと見て何調か分かる
・楽典(楽譜を読むための知識)の問題が解けて、譜読みにも応用出来る
・楽譜には書かれていない(省略されている)暗黙のルールを知っている
など
算数の問題のように
公式を覚えて問題を解くような要素と
ただ楽譜通りに弾くだけでは
お経のように表情がないので
「あめがふってきた」という文章を
・雨が降ってきた
・飴が降ってきた
・あ、目が降ってきた
どういう風に表情をつけたいのか
自分で選んで、抑揚をつけて、表現出来る
つまり、その曲に合った
タッチ・身体の使い方・調(音色のキャラクター)を
・たくさん知っている
・経験している
・自分のものにしている
など
国語(や美術)のような側面を
同時進行でやる必要があります🎹
私のお教室では
ピアノを始めたばかりの生徒さん達に
5冊の楽譜をご用意していただいて
スタートしてもらっておりますが
同じ音楽・ピアノというジャンルでありながら
科目の違う5冊の教科書(楽譜)を使って
ピアノを演奏するために必要な
色んな能力を総合的に伸ばす
ということを大切にしております🎹✧
ということを
お伝えさせていただいたのですが
今回は
24の調性と密接な関係があり
「音楽の原典」「音楽の父」と言われている
バッハの凄さについて
こちらでもシェア出来ましたら嬉しいです🥰
よく生徒さん・親御さんに
「バッハは何も知識が無い状態で聴くと
まぁ残念なことに、映えないんです🤣笑
なぜならバッハの曲は
知識が頭に入っている状態の時こそ
輝いて聴こえてくる
スルメタイプだからなんです🦑」
というお話をします。
モーツァルト、ベートーヴェン、ショパンなど
有名な作曲家達は
現代の生徒さん達と同じくバッハを勉強して
自分の曲に
バッハの音楽の技法を落とし込んでいます。
なので
真に、楽しく素敵に
有名なクラシック曲を演奏するには
バッハの音楽のテクニックが必要に
なってくるわけです🎹
さらに
バッハの凄いところの1つとして
自分の子ども達の勉強用に作曲した
《インヴェンション》や《平均律》などは
1番ハ(ド)長調
2番ハ短調
3番ニ(レ)長調
4番ニ短調
5番ホ(ミ)長調
6番ホ短調
…のように
ドレミファソラシドの長調・短調の順番で
楽譜に編纂されています。
全調で1曲ずつ曲を作るだけでも凄いのに
24曲全て
性格が全く違っていて
どの曲も美しい✧
しかも
各曲に
自分の子どもが
鍵盤楽器を学ぶための
色んなエッセンスを取り入れている✧
という
とんでもなく難しいことを
初めてやってのけた作曲家
それが
ヨハン・セバスティアン・バッハです!
これらのエピソードだけでも
バッハの凄さの片鱗が分かるかと思います😳✧
そして
実際に演奏する自分自身でも
調の性格や特徴を
感じられる・知っている・分かる
ようになっておくことの大切さも
分かるかなと思います😊
古典(クラシック)は
生きるだけなら必須ではないかもしれませんが
楽しく生きるためには必要だなぁ✧
という話を
別のブログでお話ししたことがあるのですが
【不自由な自由】
芸術を(本当の意味で)楽しむには知識が必要
そのために(それぞれのジャンルの)歴史を勉強してください。
by 村上隆さん
という様に
学ぶことで
はじめて見える景色があると
常々感じておりますよ🥰
新規生徒さん募集中です✧
ぜひこちらからお問い合わせください

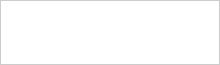
-200x200.jpeg)
-200x200.jpeg)
-200x200.jpeg)
-200x200.jpeg)
-200x200.jpeg)
-200x200.jpeg)
-200x200.jpeg)
-200x200.jpeg)
-200x200.jpeg)
-200x200.jpeg)
